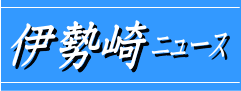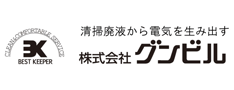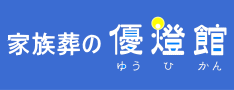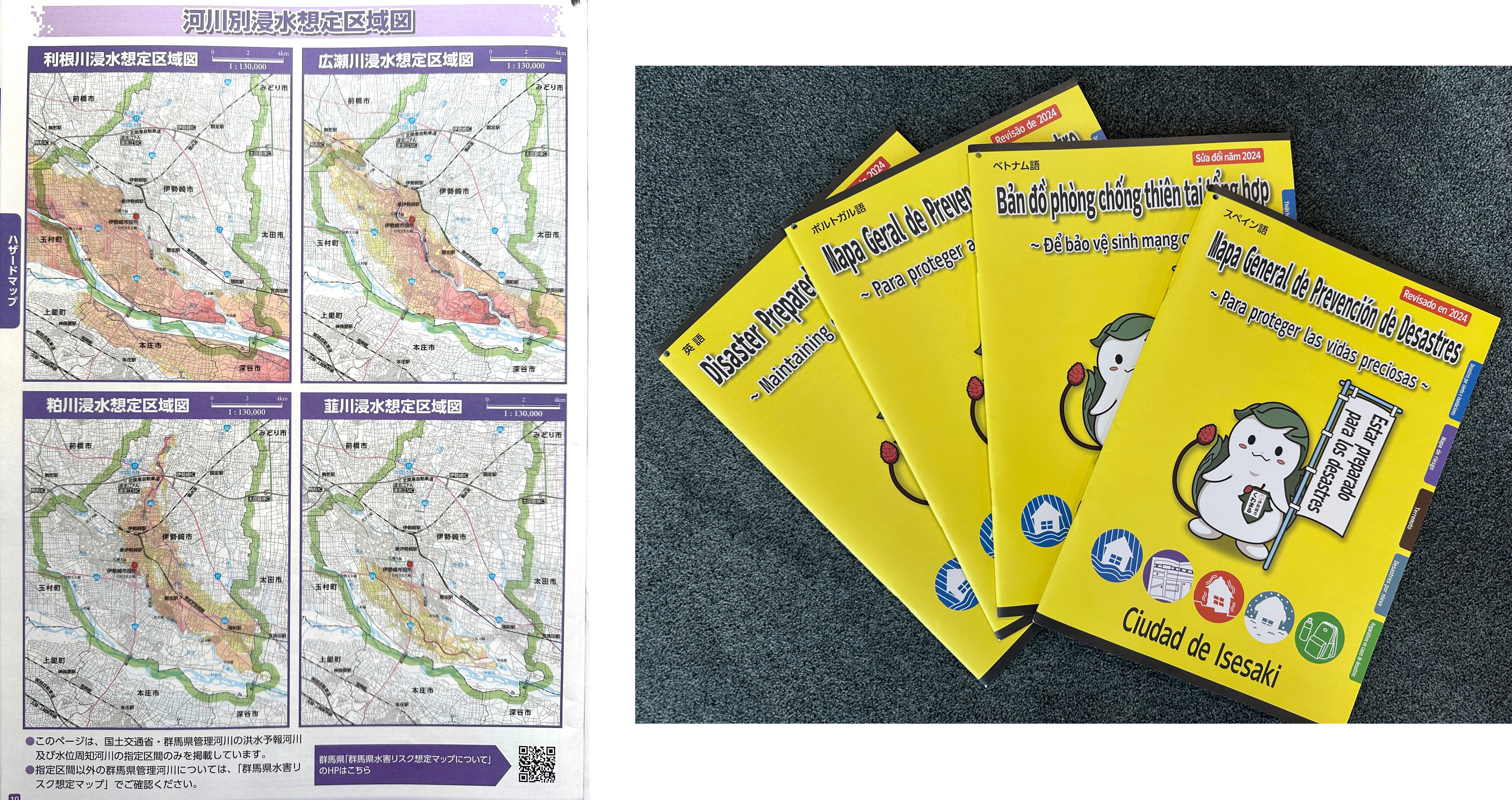議長として1年間、市内各所を訪れた。副議長としてコロナ禍を体験していただけに、その回復ぶりに「本当に良かった。飲み屋さんに友人も多いので」と素直に喜ぶ。一昨年制定の市議会基本条例に基づく、委員会を中心とした議員間討議、議案議決で賛否が分かれた場合の議員ごとの賛否公表などの取り組みも紹介。いせさきFMの議長取材依頼には、議員一人々々の紹介企画を提案した。6月中旬以降に順次放送される予定だ。
就職を考えていた農業大学校卒業の20歳の時、父の和幸さん(93歳)の町議(旧境町)出馬で就農へ。農業従事の傍ら2006年からJA佐波伊勢崎の理事を3期務めるなど、地域の農政に深く関わってきた。この間、父は旧境町の町長を3期(1991年〜2003年)務めている。その任期を終えた11年後の2014年、境地区の代表の一人として58歳で初当選。議員を目指した背景を「農業問題と土地開発」と言い切る。
農業人口の高齢化、後継者問題、農家支援など農業従事者の立場から、これまでの農政や農地開発の在り方に疑問を投げかけた。市は2025年開始の第3次総合計画策定に取り組んでいるが、各地区で一定区画の優良農地保全を呼び掛ける。都市計画区域の早期統合による「負の遺産を後世に残さない」均衡ある都市づくりを訴える。
造成中の伊勢崎南部国領産業団地に、信越化学工業の半導体材料製造工場建設が発表された。「今は第一段階に過ぎない」と今後に期待する一方、地元の境共同トレーニングセンター跡地に計画中の産業団地についても現状に触れた。従来型の団地造成ではなく、希望する規模や条件を整えて造成するオーダーメード型を強く推す。中心街活性化には将来的な夢として、伊勢崎駅周辺への市役所庁舎移転も提唱している。
合併20周年記念事業として、8月31日開催予定の本庄市、深谷市との3市連携利根川花火大会。かつて旧境町では3尺玉で人気を集めた利根川花火大会を開催していただけに、もろ手を挙げて喜ぶ。定期開催の困難さは理解の上で「市単独でも」と継続を訴える。「地域の仲間の苦しさ、喜び、やるせなさ、憤りをこれからも議員として代弁していく」と言葉に力をこめる。
300坪の畑でミカン、フェイジョア、ポポ−、バナナ・・、野菜はキュウリ、ピーマン、トマトなど、多種多様な果樹、野菜を栽培。手持ちの農業機材・資材の活用に加え、多忙な時にはパートも雇ったりする、大規模な”家庭菜園”を楽しんでいる。議員として酒席に参加する時などはその場に合わせるが、自宅の晩酌はハイボールのみ。「一晩でボトル半分、いや3分の1程度かな」と、酒量の問いに答えた。(廣瀬昭夫)
就職を考えていた農業大学校卒業の20歳の時、父の和幸さん(93歳)の町議(旧境町)出馬で就農へ。農業従事の傍ら2006年からJA佐波伊勢崎の理事を3期務めるなど、地域の農政に深く関わってきた。この間、父は旧境町の町長を3期(1991年〜2003年)務めている。その任期を終えた11年後の2014年、境地区の代表の一人として58歳で初当選。議員を目指した背景を「農業問題と土地開発」と言い切る。
農業人口の高齢化、後継者問題、農家支援など農業従事者の立場から、これまでの農政や農地開発の在り方に疑問を投げかけた。市は2025年開始の第3次総合計画策定に取り組んでいるが、各地区で一定区画の優良農地保全を呼び掛ける。都市計画区域の早期統合による「負の遺産を後世に残さない」均衡ある都市づくりを訴える。
造成中の伊勢崎南部国領産業団地に、信越化学工業の半導体材料製造工場建設が発表された。「今は第一段階に過ぎない」と今後に期待する一方、地元の境共同トレーニングセンター跡地に計画中の産業団地についても現状に触れた。従来型の団地造成ではなく、希望する規模や条件を整えて造成するオーダーメード型を強く推す。中心街活性化には将来的な夢として、伊勢崎駅周辺への市役所庁舎移転も提唱している。
合併20周年記念事業として、8月31日開催予定の本庄市、深谷市との3市連携利根川花火大会。かつて旧境町では3尺玉で人気を集めた利根川花火大会を開催していただけに、もろ手を挙げて喜ぶ。定期開催の困難さは理解の上で「市単独でも」と継続を訴える。「地域の仲間の苦しさ、喜び、やるせなさ、憤りをこれからも議員として代弁していく」と言葉に力をこめる。
300坪の畑でミカン、フェイジョア、ポポ−、バナナ・・、野菜はキュウリ、ピーマン、トマトなど、多種多様な果樹、野菜を栽培。手持ちの農業機材・資材の活用に加え、多忙な時にはパートも雇ったりする、大規模な”家庭菜園”を楽しんでいる。議員として酒席に参加する時などはその場に合わせるが、自宅の晩酌はハイボールのみ。「一晩でボトル半分、いや3分の1程度かな」と、酒量の問いに答えた。(廣瀬昭夫)