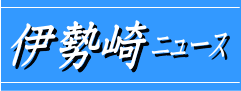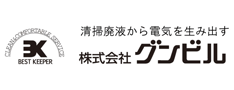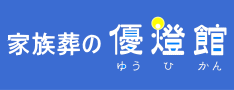【写真】上:来場者で賑わった大進建設の餅つき会場。下:社員が見守る中、子供が餅つき体験
顧客や地域に感謝を込めて、社員総出でおもてなし
住宅建築・リフォームの大進建設が餅つき大会
住宅・リフォーム建築の大進建設(伊勢崎市平和町町25-5、斎藤元秀社長)は1月19日、恒例の餅つき大会を同社敷地内で開いた。住宅計画・施工中・施工後の顧客家族や関係者、地域住民が100組近く訪れ、ついたばかりのお餅を食べながら、子供たちは餅つき体験を楽しんだ。
餅つき大会は今年で12回目。様々な家族の住宅づくりに関われてきたことへの顧客と、それを支えてくれる地域の住民に感謝を込めて、社員が総出で来場者をもてなした。8張りの大型テント内には120席のテーブル席を用意。来場者は餡やきな粉餅、からみ餅に雑煮と、つきたてのお餅に舌鼓をうった。
餅つき担当の同社社員が協力して、子供たちが餅つきを体験。最初はおそるおそるだったが、最後は上手に杵を打ち下ろしていた。子供限定で風船とポップコーン、家族には福袋がプレゼント。来場者は午前10時から午後2時まで、家族を中心につきたてのお餅を堪能した。
オムツ替え「赤ちゃんルーム」を社屋内に設置。インフルエンザなどの感染予防にと、来場の際は入り口に臨時の手洗い場を設け、手洗いと消毒を促すなど、イベント運営にあたっても、同社の家造りのコンセプトである“健康”にこだわった。
同社の家造りは住宅を建てる地中に「いやしろ炭」を埋設し、コンクリート基礎には特殊加工の微粉炭を混入。相乗効果で住環境の土台を整えている。室内仕上げでは工法や素材に加えて、身体に有害な揮発性化学物質発生を予防する、遠赤外線放射の液体スプレーを施している。(2019年1月26日)
顧客や地域に感謝を込めて、社員総出でおもてなし
住宅建築・リフォームの大進建設が餅つき大会
住宅・リフォーム建築の大進建設(伊勢崎市平和町町25-5、斎藤元秀社長)は1月19日、恒例の餅つき大会を同社敷地内で開いた。住宅計画・施工中・施工後の顧客家族や関係者、地域住民が100組近く訪れ、ついたばかりのお餅を食べながら、子供たちは餅つき体験を楽しんだ。
餅つき大会は今年で12回目。様々な家族の住宅づくりに関われてきたことへの顧客と、それを支えてくれる地域の住民に感謝を込めて、社員が総出で来場者をもてなした。8張りの大型テント内には120席のテーブル席を用意。来場者は餡やきな粉餅、からみ餅に雑煮と、つきたてのお餅に舌鼓をうった。
餅つき担当の同社社員が協力して、子供たちが餅つきを体験。最初はおそるおそるだったが、最後は上手に杵を打ち下ろしていた。子供限定で風船とポップコーン、家族には福袋がプレゼント。来場者は午前10時から午後2時まで、家族を中心につきたてのお餅を堪能した。
オムツ替え「赤ちゃんルーム」を社屋内に設置。インフルエンザなどの感染予防にと、来場の際は入り口に臨時の手洗い場を設け、手洗いと消毒を促すなど、イベント運営にあたっても、同社の家造りのコンセプトである“健康”にこだわった。
同社の家造りは住宅を建てる地中に「いやしろ炭」を埋設し、コンクリート基礎には特殊加工の微粉炭を混入。相乗効果で住環境の土台を整えている。室内仕上げでは工法や素材に加えて、身体に有害な揮発性化学物質発生を予防する、遠赤外線放射の液体スプレーを施している。(2019年1月26日)