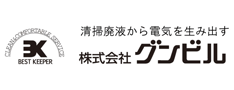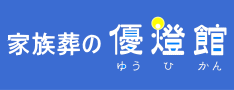映画の舞台となったトイレの「TOKYOTOIRETプロジェクト」の紹介チラシ
【モトコ・リッチ東京支局長】
公衆トイレが心を揺さぶり芸術的なインスピレーションが得られるということは通常ありえない。
そしてまた、東京の銭湯にあるようなトイレというのは世界でも稀である。
だからこそ、『パリ、テキサス』や『欲望の翼』のようなアート系の人気作を手がけたドイツ人映画監督ヴィム・ヴェンダースは、2022年の春に初めて日本の首都周辺の公衆トイレを十数か所見学したとき、安藤忠雄、坂茂、隈研吾らプリツカー賞受賞者がデザインした「小さな宝石」と形容されるものに魅了された。これらのスタイリッシュな便器は、アカデミー賞の国際長編部門にノミネートされ、2月7日にアメリカで公開される彼の最新作『パーフェクトデイズ』の着想に火をつけることこととなった。
この映画は、謎めいた過去を持つ公衆トイレの清掃員が、質素な生活を送りながら職人のように丁寧に働く姿を描いた切ない人間ドラマであるが、実はある種の宣伝活動がきっかけであった。ヴェンダース監督は、日本の著名な実業家のゲストとして日本に招かれたのだが、その実業家はヴェンダース監督に、日本の芸術性と衛生技術のショーケースとして考案されたトイレを題材にした短編映画シリーズを撮ってほしいと考えていたのだ
ファーストリテイリング(ユニクロで知られる衣料品大手)の創業者の息子であり、同社の上級執行役員である柳井康治氏は、「日本の誇り」を建築によって表現する公衆トイレ・プロジェクトの陣頭指揮を執っていた。
「日本のトイレが世界一だと言っても、誰も異論はないでしょう」と柳井氏は昨年末のインタビューで語っている。柳井氏は、公共施設を芸術と同じように公益的なものとするため、独特の美的感覚を持つ建築家を採用したのである。
当初は2020年に予定されていた夏季オリンピックのために世界を歓迎するために建設されたものだったが、パンデミックによって大会が2021年に延期され、無観客で開催されたため、計画はその機会を得られなかった。
オリンピック・デビューが失敗に終わった後、柳井氏は別のプロモーションの道を模索していた。日本最大の広告会社である電通のクリエイティブ・ディレクターで脚本家の高崎卓馬氏に連絡を取り、トイレを国際的にアピールする計画を練った。
高崎氏は、クエンティン・タランティーノやマーティン・スコセッシ、スティーブン・スピルバーグといった映画監督を起用することを提案した。大学時代に『パリ、テキサス』を見て以来のファンである柳井氏は、ヴェンダース監督が日本に強い関心を持っており、日本の偉大な監督である小津安二郎へのオマージュであり映像日記であるドキュメンタリー『東京画』を制作していたことを思い出した。
招待状が届いたときは、パンデミックの真っ最中で、ヴェンダース監督は8年ぶりに訪れた日本にある種の郷愁を感じていた。昨年秋、ヴェンダース監督が審査委員長を務めていた東京国際映画祭の会期中、むき出しの会議室で、スタッフが彼の前に並べたチョコレートの包み紙を剥がしながら、「東京はいつも不思議と落ち着くんだ」と言っていた。
ベルリン出身のヴェンダース監督は、パンデミック(世界的大流行)の際に、住民が自宅近くの公園を荒らしたことから、市民の心の荒廃に落胆した。東京、とりわけデザイナーズ・トイレに、彼は清潔さや地域社会の協力といった純粋な精神の体現を見たのだ。
「これほど細部にまで気を配ったトイレは、世界中どこを探しても見たことがない」とヴェンダース監督は言った。彼はこの清掃員の働き(一般的な公衆トイレの清掃が1日1回であるのに対し、柳井氏は清掃員に資金を提供し、毎日2〜3回、建築トイレの手入れをさせている)を市民の精神の賜物と捉えた。
東京を離れる前、ヴェンダース監督はトイレ清掃員を主人公にした長編映画を撮りたいと考えていた。柳井氏は、1996年の恋愛ドラマ「シャル・ウィ・ダンス?」で主演を務めて以来、国際的な人気を博した日本で最も有名な俳優の一人、役所広司氏を推薦していた。
物語を作り始めるにあたって、ヴェンダース監督は主人公がどこに住むかを知る必要があると感じた。ヴェンダース監督は東京取材旅行の最後の数日間をロケ地巡りに費やした。彼は、スカイツリーの影に低層アパートがひっそりと佇む、東京の東部にある労働者の街、押上に決めた。
「私にとって、この界隈は欠かすことのできない場所だった」とヴェンダース監督は言う。「カメラを構えるためには、その場所を愛する必要があるんだよ」。
監督がベルリンに戻った直後、高崎氏が加わり、わずか3週間で全編日本語の脚本を練り上げた。
ヴェンダース監督は、細部にまで静かな注意を払い、大切にしているカセットテープや地面に落ちた木の葉の影に喜びを見出すような人物像を作り上げた。監督は憧れの小津監督に倣い、小津の代表作のひとつとされる『東京物語』に登場する一家の名前にちなんで、平山という名をこのトイレ清掃員につけた。
ヴェンダース監督は、必要なものだけに絞り込まれた日常を構想するにあたり、このキャラクターを「持たざることの美しき象徴」にしたいと考えた。
「削減することは現代文明の大きな課題のひとつだ」とヴェンダース監督は言う。「そして、私たち自身の無駄を無くしていく方法を学ばなければ、地球と気候をより良くすることはできない」
2022年の秋に撮影が始まる前、監督と役所氏は、主人公が自宅で大切にしている観葉植物の手入れをしたり、寝室の整然とした棚からフォークナーの翻訳作品を読んだりする様子を撮影するアパートを訪れた。ヴェンダース監督は役者に、美術監督から提供された小道具を合理化し、登場人物にとって最も重要なものだけを残すことを考えるように頼んだ。
「私はこう自問自答するんです―本当にそんなものを持っているだろうか?と」 役所氏は昨年末、レンタルオフィスでの会見で当時をこう振り返った。 「そうやって現実的でないものを取り除いていくのです」
役所氏は2日間、特注の道具の使い方を含め、トイレ掃除の技術を学んだ。彼は、ヴェンダース監督がドキュメンタリーを撮っているかのように演じたいと言った。監督は、これほど完全にそのキャラクターになりきった俳優と仕事をしたのは初めてだと語った。役所氏は昨年春のカンヌ国際映画祭で最優秀男優賞を受賞している。
ヴェンダースは、2022年の秋に記者が撮影現場を訪れたとき、坂茂が設計した公衆トイレのひとつで、紫、赤、黄色の半透明のパネルが貼られた長方形のガラス張りの建物で、利用者がトイレのドアの鍵を閉めると不透明になるもののシーンを撮影していた。
青いジャンプスーツに身を包んだ役所は、腰に工具ベルトを巻き、青いゴム手袋と白いスニーカーを履いていた。彼は通訳を介してヴェンダース監督に短い打ち合わせした。グレー・ベージュのリネンのスリーピース・スーツに黒ぶちメガネ、黒の布製スニーカーという出で立ちの監督が「アクション!」と声をかけると、役所はバケツとゴミ袋2つ、トイレットペーパー1つを持って中央の個室に入り、エキストラは両脇の個室に入った。
午後の光が弱まり、15日間の撮影スケジュールの緊張感が撮影現場に漂い始めた。撮影の合間には、役所がトイレのゴミ箱を掃除するために、スタッフがトイレのゴミ箱にゴミを詰めた。業を煮やしたヴェンダース監督が「あっちへ行け!」と叫ぶと、クルーは小走りで自転車の陰に隠れた。
ヴェンダース監督は、この撮影はこれまでで最も短いものだったと語っており、その無駄のない撮影技術は映画の最小主義的なコンセプトを反映している。
庄司かおりは日経アジアに寄稿し、この映画を「禅僧との問答のようで、相手には疑問ばかりが残るが、不思議な静けさが漂う」と評し、主人公の仕事への献身を「ほとんどの日本人が当たり前のこととして受け止めている。仕事の重要性は疑いもなく、生まれたときから私たちに叩き込まれているものだ」としている。
だが、このキャラクターが非現実的なファンタジーだと感じるものもいる。低賃金で薄汚れた仕事に満足し、孤立した生活を送る男は、日本人の平穏さに価値を見出す「男性や西洋人の夢」だと、東京大学の林香織教授(メディア論)は言う。「これを素晴らしいと思うのは、すでにお金持ちで、詰め込みすぎの役員スケジュールから逃れたい人たちだ」と林教授は言う。
役所氏は、唯足るを知る男という描写が理想主義的に見えることを認めている。
「多くの人間は、欲しいものを手に入れると、すぐに別のものが欲しくなり始める」と彼は言う。 「その考えからは決して逃れることはできない」
しかし、たとえそのキャラクターが「理想的すぎて、現実には存在しない」ものであったとしても、「そうなろうと努力することには価値がある」と役所氏は言った。
【翻訳】星大吾(ほしだいご):伊勢崎市中央町在住。新潟大学農学部卒業。白鳳大学法科大学院終了。専門は契約書・学術論文。2022年、伊勢崎市の外国籍児童のための日本語教室「子ども日本語教室未来塾」代表。問い合わせは:h044195@gmail.comへ。
トイレが主役になった映画「パーフェクトデイズ」
ニューヨークタイムズ 映画欄記事(2024年2月3日付)
ニューヨークタイムズ 映画欄記事(2024年2月3日付)
【モトコ・リッチ東京支局長】
公衆トイレが心を揺さぶり芸術的なインスピレーションが得られるということは通常ありえない。
そしてまた、東京の銭湯にあるようなトイレというのは世界でも稀である。
だからこそ、『パリ、テキサス』や『欲望の翼』のようなアート系の人気作を手がけたドイツ人映画監督ヴィム・ヴェンダースは、2022年の春に初めて日本の首都周辺の公衆トイレを十数か所見学したとき、安藤忠雄、坂茂、隈研吾らプリツカー賞受賞者がデザインした「小さな宝石」と形容されるものに魅了された。これらのスタイリッシュな便器は、アカデミー賞の国際長編部門にノミネートされ、2月7日にアメリカで公開される彼の最新作『パーフェクトデイズ』の着想に火をつけることこととなった。
この映画は、謎めいた過去を持つ公衆トイレの清掃員が、質素な生活を送りながら職人のように丁寧に働く姿を描いた切ない人間ドラマであるが、実はある種の宣伝活動がきっかけであった。ヴェンダース監督は、日本の著名な実業家のゲストとして日本に招かれたのだが、その実業家はヴェンダース監督に、日本の芸術性と衛生技術のショーケースとして考案されたトイレを題材にした短編映画シリーズを撮ってほしいと考えていたのだ
ファーストリテイリング(ユニクロで知られる衣料品大手)の創業者の息子であり、同社の上級執行役員である柳井康治氏は、「日本の誇り」を建築によって表現する公衆トイレ・プロジェクトの陣頭指揮を執っていた。
「日本のトイレが世界一だと言っても、誰も異論はないでしょう」と柳井氏は昨年末のインタビューで語っている。柳井氏は、公共施設を芸術と同じように公益的なものとするため、独特の美的感覚を持つ建築家を採用したのである。
当初は2020年に予定されていた夏季オリンピックのために世界を歓迎するために建設されたものだったが、パンデミックによって大会が2021年に延期され、無観客で開催されたため、計画はその機会を得られなかった。
オリンピック・デビューが失敗に終わった後、柳井氏は別のプロモーションの道を模索していた。日本最大の広告会社である電通のクリエイティブ・ディレクターで脚本家の高崎卓馬氏に連絡を取り、トイレを国際的にアピールする計画を練った。
高崎氏は、クエンティン・タランティーノやマーティン・スコセッシ、スティーブン・スピルバーグといった映画監督を起用することを提案した。大学時代に『パリ、テキサス』を見て以来のファンである柳井氏は、ヴェンダース監督が日本に強い関心を持っており、日本の偉大な監督である小津安二郎へのオマージュであり映像日記であるドキュメンタリー『東京画』を制作していたことを思い出した。
招待状が届いたときは、パンデミックの真っ最中で、ヴェンダース監督は8年ぶりに訪れた日本にある種の郷愁を感じていた。昨年秋、ヴェンダース監督が審査委員長を務めていた東京国際映画祭の会期中、むき出しの会議室で、スタッフが彼の前に並べたチョコレートの包み紙を剥がしながら、「東京はいつも不思議と落ち着くんだ」と言っていた。
ベルリン出身のヴェンダース監督は、パンデミック(世界的大流行)の際に、住民が自宅近くの公園を荒らしたことから、市民の心の荒廃に落胆した。東京、とりわけデザイナーズ・トイレに、彼は清潔さや地域社会の協力といった純粋な精神の体現を見たのだ。
「これほど細部にまで気を配ったトイレは、世界中どこを探しても見たことがない」とヴェンダース監督は言った。彼はこの清掃員の働き(一般的な公衆トイレの清掃が1日1回であるのに対し、柳井氏は清掃員に資金を提供し、毎日2〜3回、建築トイレの手入れをさせている)を市民の精神の賜物と捉えた。
東京を離れる前、ヴェンダース監督はトイレ清掃員を主人公にした長編映画を撮りたいと考えていた。柳井氏は、1996年の恋愛ドラマ「シャル・ウィ・ダンス?」で主演を務めて以来、国際的な人気を博した日本で最も有名な俳優の一人、役所広司氏を推薦していた。
物語を作り始めるにあたって、ヴェンダース監督は主人公がどこに住むかを知る必要があると感じた。ヴェンダース監督は東京取材旅行の最後の数日間をロケ地巡りに費やした。彼は、スカイツリーの影に低層アパートがひっそりと佇む、東京の東部にある労働者の街、押上に決めた。
「私にとって、この界隈は欠かすことのできない場所だった」とヴェンダース監督は言う。「カメラを構えるためには、その場所を愛する必要があるんだよ」。
監督がベルリンに戻った直後、高崎氏が加わり、わずか3週間で全編日本語の脚本を練り上げた。
ヴェンダース監督は、細部にまで静かな注意を払い、大切にしているカセットテープや地面に落ちた木の葉の影に喜びを見出すような人物像を作り上げた。監督は憧れの小津監督に倣い、小津の代表作のひとつとされる『東京物語』に登場する一家の名前にちなんで、平山という名をこのトイレ清掃員につけた。
ヴェンダース監督は、必要なものだけに絞り込まれた日常を構想するにあたり、このキャラクターを「持たざることの美しき象徴」にしたいと考えた。
「削減することは現代文明の大きな課題のひとつだ」とヴェンダース監督は言う。「そして、私たち自身の無駄を無くしていく方法を学ばなければ、地球と気候をより良くすることはできない」
2022年の秋に撮影が始まる前、監督と役所氏は、主人公が自宅で大切にしている観葉植物の手入れをしたり、寝室の整然とした棚からフォークナーの翻訳作品を読んだりする様子を撮影するアパートを訪れた。ヴェンダース監督は役者に、美術監督から提供された小道具を合理化し、登場人物にとって最も重要なものだけを残すことを考えるように頼んだ。
「私はこう自問自答するんです―本当にそんなものを持っているだろうか?と」 役所氏は昨年末、レンタルオフィスでの会見で当時をこう振り返った。 「そうやって現実的でないものを取り除いていくのです」
役所氏は2日間、特注の道具の使い方を含め、トイレ掃除の技術を学んだ。彼は、ヴェンダース監督がドキュメンタリーを撮っているかのように演じたいと言った。監督は、これほど完全にそのキャラクターになりきった俳優と仕事をしたのは初めてだと語った。役所氏は昨年春のカンヌ国際映画祭で最優秀男優賞を受賞している。
ヴェンダースは、2022年の秋に記者が撮影現場を訪れたとき、坂茂が設計した公衆トイレのひとつで、紫、赤、黄色の半透明のパネルが貼られた長方形のガラス張りの建物で、利用者がトイレのドアの鍵を閉めると不透明になるもののシーンを撮影していた。
青いジャンプスーツに身を包んだ役所は、腰に工具ベルトを巻き、青いゴム手袋と白いスニーカーを履いていた。彼は通訳を介してヴェンダース監督に短い打ち合わせした。グレー・ベージュのリネンのスリーピース・スーツに黒ぶちメガネ、黒の布製スニーカーという出で立ちの監督が「アクション!」と声をかけると、役所はバケツとゴミ袋2つ、トイレットペーパー1つを持って中央の個室に入り、エキストラは両脇の個室に入った。
午後の光が弱まり、15日間の撮影スケジュールの緊張感が撮影現場に漂い始めた。撮影の合間には、役所がトイレのゴミ箱を掃除するために、スタッフがトイレのゴミ箱にゴミを詰めた。業を煮やしたヴェンダース監督が「あっちへ行け!」と叫ぶと、クルーは小走りで自転車の陰に隠れた。
ヴェンダース監督は、この撮影はこれまでで最も短いものだったと語っており、その無駄のない撮影技術は映画の最小主義的なコンセプトを反映している。
庄司かおりは日経アジアに寄稿し、この映画を「禅僧との問答のようで、相手には疑問ばかりが残るが、不思議な静けさが漂う」と評し、主人公の仕事への献身を「ほとんどの日本人が当たり前のこととして受け止めている。仕事の重要性は疑いもなく、生まれたときから私たちに叩き込まれているものだ」としている。
だが、このキャラクターが非現実的なファンタジーだと感じるものもいる。低賃金で薄汚れた仕事に満足し、孤立した生活を送る男は、日本人の平穏さに価値を見出す「男性や西洋人の夢」だと、東京大学の林香織教授(メディア論)は言う。「これを素晴らしいと思うのは、すでにお金持ちで、詰め込みすぎの役員スケジュールから逃れたい人たちだ」と林教授は言う。
役所氏は、唯足るを知る男という描写が理想主義的に見えることを認めている。
「多くの人間は、欲しいものを手に入れると、すぐに別のものが欲しくなり始める」と彼は言う。 「その考えからは決して逃れることはできない」
しかし、たとえそのキャラクターが「理想的すぎて、現実には存在しない」ものであったとしても、「そうなろうと努力することには価値がある」と役所氏は言った。
【翻訳】星大吾(ほしだいご):伊勢崎市中央町在住。新潟大学農学部卒業。白鳳大学法科大学院終了。専門は契約書・学術論文。2022年、伊勢崎市の外国籍児童のための日本語教室「子ども日本語教室未来塾」代表。問い合わせは:h044195@gmail.comへ。