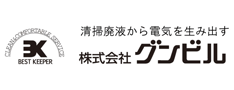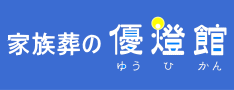アイヌのアイデンティティのひとつだった北海道のサケの川漁
米国の高級紙、ニューヨークタイムズ。その社説から、日本人にとって関心が深いと思われるテーマ、米国からみた緊張高まる国際情勢の捉え方など、わかりやすい翻訳でお届けしています(電子版掲載から本サイト掲載までの時間経過あり)。伊勢崎市在住の翻訳家、星大吾さんの協力を得ました。
アイヌ先住民族を代表する団体が、100年以上前に失われたアイヌ民族が北海道の川でサケを自由に漁獲する権利を取り戻すため起こした訴訟。様々な関係者の思いはー。
モトコ リッチ、ヒカリ ヒダ
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
ある日の午後、差間正樹氏は霧の中から日本最北の地、北海道・十勝川の灰色の水面を見つめた。彼のルーツであるアイヌ民族は、かつてここから銛や網を使って神からの贈り物とされるサケを獲っていた。
日本の法律では、アイヌの料理や交易、精神文化に欠かせないサケの川漁は、100年以上前から禁止されている。72歳の差間氏は、今こそアイヌの人々にとっての当然の権利を取り戻し、衰退したアイヌのアイデンティティの最後の名残のひとつを取り戻す時だと語った。
「かつての我々の文化では、サケはコミュニティーの中で誰もが楽しめるものでした。サケは我々のためにあり、我々はこの魚を獲る権利を取り戻ししたいのです。」
国会でアイヌを先住民族と認める法律が可決されてから4年が経ち、差間氏はサケ漁の権利を取り戻すために国と県を提訴する団体を率いている。
日本の同化政策によって、何世紀にもわたり、アイヌは土地を奪われ、狩猟や漁業をやめ、農業やその他の単純労働に従事させられ、自分たちの言語を使うことのできない日本語学校に押し込められた。
明治時代(1868〜1912)、政府が川での漁を全面的に禁止したのは、太平洋に産卵に向かうサケの資源を保護するためだった。
アイヌの歴史と漁業権について著書がある札幌学院大学の山田伸一教授(人間科学)は、「この動きは、海からサケを獲る日本の漁師に有利になるよう、アイヌを生業としての漁業から遠ざけようとする政府の政策と一致していた」と語る。
アイヌの擁護者たちは、日本の法律は、伝統的な所有権や慣習によって主張される土地や資源を利用する権利を規定する「先住民族の権利に関する国連宣言」を遵守していないと言う。日本は2007年、この宣言(但し強制力はない)に同意した。
「日本は法の支配に従うというが、先住民族の権利という点では非常に遅れている」と、北海道東部にある私立博物館の館長であり、日本の国会議員を務めた唯一のアイヌ人の子孫である萱野志朗氏は言う。「アイヌの人々は、伝統的なアイヌのライフスタイルに戻るという選択肢を持つべきだ。」
アイヌの人数は著しく減少しており、2017年に実施された最後の公式調査では、総人口約520万人の北海道でアイヌと確認されたのは13,118人だけだった。ユネスコはアイヌ語を 「危機的消滅危機言語 」に指定している。
日本政府は今年、アイヌを先住民族として認定した2019年の法律に基づき、アイヌの文化活動、観光、産業を支援するために約56億円を支出する予定だ。この新法は、10年前の旧決議に基づくものである。
2020年、政府は県庁所在地である札幌市の南、白老にアイヌ民族博物館を開館し、舞踊、木彫り、弓矢、刺繍などのアイヌの伝統を紹介している。メインの展示室にある歴史年表は、日本の侵略者がアイヌを「抑圧」し、人口の一部を絶滅させる病気をもたらし、日本の習慣を強制し、「しばしば耕作不可能な」農地をアイヌに与えたことを認めている。
新法も国立アイヌ民族博物館・公園(ウポポイ)の存在も、日本を単一民族の国だと主張する日本の政治家たちに何世紀も無視されてきたアイヌに力を与えるには足りないと言う批判もある。
政府はアイヌの工芸品、音楽、舞踊を重視しているが、アイヌの権利の専門家であり、著名なアイヌ指導者の姪でもある鵜沢加奈子氏は「私たちは政治的権利を持つべきです。」と言う。
北海道の先住民族の存在を教科書やカリキュラムでほとんど認めていない教育制度の中で、アイヌの一部の人々は、切り離された博物館以上のものを望んでいるという。
アイヌ民族博物館の副館長である村木美幸氏(63歳)は、子どもの頃、家族がアイヌ民族であることを家庭で話したことはなく、クラスメートは自分や他のアイヌの子どもたちを犬に例えたという。
「社会全体では、私たちが学ぶのは日本文化だけです。それは私たちの数が少ないからだと言います。でもそれは、私たちが自由に生きられなかったせいでもあるのです。」と彼女は言う。
差間氏にとって、それはアイヌがいつでも川からサケを獲れるようになって初めて可能になることなのだ。
県知事は毎年、儀式のために限られた数のサケを捕ることをアイヌに認めている。差間氏によれば、仮にラポロ・アイヌ・ネイションが勝訴したとしても、毎年定期的に許可されている100匹や200匹以上のサケを捕獲することはないという。
「魚の数ではなく、私たちの権利の問題なのです」と、地元で漁網を製造する会社を共同経営し、海の商業漁業免許を持つ差間氏は語った。
この裁判は早ければ今秋にも法廷で審理される可能性がある。日本政府は裁判所に提出した資料の中で、川漁の禁止は北海道のすべての住民を対象としており、アイヌは年に一度の儀式を除いて特別な権利を与えられていないと述べている。
北海道庁アイヌ政策課の遠藤通昭広報官は、係争中の訴訟を理由にコメントを避けた。内閣官房のアイヌ政策推進会議と国の水産庁もコメントを避けている。
北海道のアイヌ・コミュニティ内でも、アイヌ文化を守るための最善の方法をめぐっては意見が分かれている。
北海道アイヌ協会の貝澤和明事務局長は、土地や森林へのアクセス権とともに漁業権についても政府関係者に働きかけたいと述べた。
ウポポイ博物館でアイヌ文化に携わる人々は、法廷闘争よりも自分たちの文化的ルーツを探求していると語った。
午後、伝統的な木製のカヌーを実演している博物館職員の牟田達明氏(34)は、「訴訟はとても重要ですが、同時に私たちは現代の日本人です。法律に従うべきではないでしょうか?」と語った。
ラポロ・アイヌ・ネイションのメンバー12人のうち数人は(ほとんど全員が差間氏の下で働いている)、訴訟の過程で自分たちのルーツを発見した。
子供の頃、長根弘喜氏(38)はアイヌはすでに絶滅したと思っていた。まさか自分がアイヌであるとは思ってもみなかった。
ある日の午後、長根氏は地元の公民館のテーブルで、他の数人のメンバーとともに、藍色の布に黄色い糸を針で刺す作業に没頭していた。教師の廣川和子(64)は、長い間ロープを編んだり大きな網を張ったりして硬くなった太い指にもかかわらず、伝統的な刺繍が上手だと彼をからかった。
差間氏にとって、訴訟を起こしアイヌの伝統を守ることは、遺産を残すことでもある。他の多くのアイヌの人たちと同じように、彼は子供の頃、自分が先住民族の一員であることをなんとなく感じてはいたが、はっきりと自覚したことはなかった。
しかし40代の頃、アイヌの血を引いていることを嘲笑され、バーで乱闘騒ぎを起こした。その時、彼は自分の人生を文化と政治活動に捧げることを決意した。
「刺繍や木彫りに誰も興味を示さないときでも、一人で頑張りました」と涙を流しながら語った。「民族差別はどこに行ってもなくならない。どこにも隠れることはできないのです。」
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
星大吾(ほしだいご):1974年生まれ、伊勢崎市中央町在住。伊勢崎第二中、足利学園(現白鳳大学足利高校)、新潟大学農学部卒業。白鳳大学法科大学院終了。2019年、翻訳家として開業。専門は契約書・学術論文。2022年、伊勢崎市の外国籍児童のための日本語教室「子ども日本語教室未来塾」代表。同年、英米児童文学研究者として論文「The Borrowers」における空間と時間 人文地理学的解説」(英語圏児童文学研究第67号)発表。問い合わせは:h044195@gmail.comへ。
法制化の中、アイヌ民族のアイデンティティを取り戻す戦い
地元プロが翻訳 NYT アジア太平洋欄記事(2023年7月2日付)
地元プロが翻訳 NYT アジア太平洋欄記事(2023年7月2日付)
米国の高級紙、ニューヨークタイムズ。その社説から、日本人にとって関心が深いと思われるテーマ、米国からみた緊張高まる国際情勢の捉え方など、わかりやすい翻訳でお届けしています(電子版掲載から本サイト掲載までの時間経過あり)。伊勢崎市在住の翻訳家、星大吾さんの協力を得ました。
アイヌ先住民族を代表する団体が、100年以上前に失われたアイヌ民族が北海道の川でサケを自由に漁獲する権利を取り戻すため起こした訴訟。様々な関係者の思いはー。
モトコ リッチ、ヒカリ ヒダ
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
ある日の午後、差間正樹氏は霧の中から日本最北の地、北海道・十勝川の灰色の水面を見つめた。彼のルーツであるアイヌ民族は、かつてここから銛や網を使って神からの贈り物とされるサケを獲っていた。
日本の法律では、アイヌの料理や交易、精神文化に欠かせないサケの川漁は、100年以上前から禁止されている。72歳の差間氏は、今こそアイヌの人々にとっての当然の権利を取り戻し、衰退したアイヌのアイデンティティの最後の名残のひとつを取り戻す時だと語った。
「かつての我々の文化では、サケはコミュニティーの中で誰もが楽しめるものでした。サケは我々のためにあり、我々はこの魚を獲る権利を取り戻ししたいのです。」
国会でアイヌを先住民族と認める法律が可決されてから4年が経ち、差間氏はサケ漁の権利を取り戻すために国と県を提訴する団体を率いている。
日本の同化政策によって、何世紀にもわたり、アイヌは土地を奪われ、狩猟や漁業をやめ、農業やその他の単純労働に従事させられ、自分たちの言語を使うことのできない日本語学校に押し込められた。
明治時代(1868〜1912)、政府が川での漁を全面的に禁止したのは、太平洋に産卵に向かうサケの資源を保護するためだった。
アイヌの歴史と漁業権について著書がある札幌学院大学の山田伸一教授(人間科学)は、「この動きは、海からサケを獲る日本の漁師に有利になるよう、アイヌを生業としての漁業から遠ざけようとする政府の政策と一致していた」と語る。
アイヌの擁護者たちは、日本の法律は、伝統的な所有権や慣習によって主張される土地や資源を利用する権利を規定する「先住民族の権利に関する国連宣言」を遵守していないと言う。日本は2007年、この宣言(但し強制力はない)に同意した。
「日本は法の支配に従うというが、先住民族の権利という点では非常に遅れている」と、北海道東部にある私立博物館の館長であり、日本の国会議員を務めた唯一のアイヌ人の子孫である萱野志朗氏は言う。「アイヌの人々は、伝統的なアイヌのライフスタイルに戻るという選択肢を持つべきだ。」
アイヌの人数は著しく減少しており、2017年に実施された最後の公式調査では、総人口約520万人の北海道でアイヌと確認されたのは13,118人だけだった。ユネスコはアイヌ語を 「危機的消滅危機言語 」に指定している。
日本政府は今年、アイヌを先住民族として認定した2019年の法律に基づき、アイヌの文化活動、観光、産業を支援するために約56億円を支出する予定だ。この新法は、10年前の旧決議に基づくものである。
2020年、政府は県庁所在地である札幌市の南、白老にアイヌ民族博物館を開館し、舞踊、木彫り、弓矢、刺繍などのアイヌの伝統を紹介している。メインの展示室にある歴史年表は、日本の侵略者がアイヌを「抑圧」し、人口の一部を絶滅させる病気をもたらし、日本の習慣を強制し、「しばしば耕作不可能な」農地をアイヌに与えたことを認めている。
新法も国立アイヌ民族博物館・公園(ウポポイ)の存在も、日本を単一民族の国だと主張する日本の政治家たちに何世紀も無視されてきたアイヌに力を与えるには足りないと言う批判もある。
政府はアイヌの工芸品、音楽、舞踊を重視しているが、アイヌの権利の専門家であり、著名なアイヌ指導者の姪でもある鵜沢加奈子氏は「私たちは政治的権利を持つべきです。」と言う。
北海道の先住民族の存在を教科書やカリキュラムでほとんど認めていない教育制度の中で、アイヌの一部の人々は、切り離された博物館以上のものを望んでいるという。
アイヌ民族博物館の副館長である村木美幸氏(63歳)は、子どもの頃、家族がアイヌ民族であることを家庭で話したことはなく、クラスメートは自分や他のアイヌの子どもたちを犬に例えたという。
「社会全体では、私たちが学ぶのは日本文化だけです。それは私たちの数が少ないからだと言います。でもそれは、私たちが自由に生きられなかったせいでもあるのです。」と彼女は言う。
差間氏にとって、それはアイヌがいつでも川からサケを獲れるようになって初めて可能になることなのだ。
県知事は毎年、儀式のために限られた数のサケを捕ることをアイヌに認めている。差間氏によれば、仮にラポロ・アイヌ・ネイションが勝訴したとしても、毎年定期的に許可されている100匹や200匹以上のサケを捕獲することはないという。
「魚の数ではなく、私たちの権利の問題なのです」と、地元で漁網を製造する会社を共同経営し、海の商業漁業免許を持つ差間氏は語った。
この裁判は早ければ今秋にも法廷で審理される可能性がある。日本政府は裁判所に提出した資料の中で、川漁の禁止は北海道のすべての住民を対象としており、アイヌは年に一度の儀式を除いて特別な権利を与えられていないと述べている。
北海道庁アイヌ政策課の遠藤通昭広報官は、係争中の訴訟を理由にコメントを避けた。内閣官房のアイヌ政策推進会議と国の水産庁もコメントを避けている。
北海道のアイヌ・コミュニティ内でも、アイヌ文化を守るための最善の方法をめぐっては意見が分かれている。
北海道アイヌ協会の貝澤和明事務局長は、土地や森林へのアクセス権とともに漁業権についても政府関係者に働きかけたいと述べた。
ウポポイ博物館でアイヌ文化に携わる人々は、法廷闘争よりも自分たちの文化的ルーツを探求していると語った。
午後、伝統的な木製のカヌーを実演している博物館職員の牟田達明氏(34)は、「訴訟はとても重要ですが、同時に私たちは現代の日本人です。法律に従うべきではないでしょうか?」と語った。
ラポロ・アイヌ・ネイションのメンバー12人のうち数人は(ほとんど全員が差間氏の下で働いている)、訴訟の過程で自分たちのルーツを発見した。
子供の頃、長根弘喜氏(38)はアイヌはすでに絶滅したと思っていた。まさか自分がアイヌであるとは思ってもみなかった。
ある日の午後、長根氏は地元の公民館のテーブルで、他の数人のメンバーとともに、藍色の布に黄色い糸を針で刺す作業に没頭していた。教師の廣川和子(64)は、長い間ロープを編んだり大きな網を張ったりして硬くなった太い指にもかかわらず、伝統的な刺繍が上手だと彼をからかった。
差間氏にとって、訴訟を起こしアイヌの伝統を守ることは、遺産を残すことでもある。他の多くのアイヌの人たちと同じように、彼は子供の頃、自分が先住民族の一員であることをなんとなく感じてはいたが、はっきりと自覚したことはなかった。
しかし40代の頃、アイヌの血を引いていることを嘲笑され、バーで乱闘騒ぎを起こした。その時、彼は自分の人生を文化と政治活動に捧げることを決意した。
「刺繍や木彫りに誰も興味を示さないときでも、一人で頑張りました」と涙を流しながら語った。「民族差別はどこに行ってもなくならない。どこにも隠れることはできないのです。」
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
星大吾(ほしだいご):1974年生まれ、伊勢崎市中央町在住。伊勢崎第二中、足利学園(現白鳳大学足利高校)、新潟大学農学部卒業。白鳳大学法科大学院終了。2019年、翻訳家として開業。専門は契約書・学術論文。2022年、伊勢崎市の外国籍児童のための日本語教室「子ども日本語教室未来塾」代表。同年、英米児童文学研究者として論文「The Borrowers」における空間と時間 人文地理学的解説」(英語圏児童文学研究第67号)発表。問い合わせは:h044195@gmail.comへ。